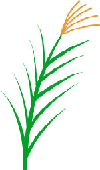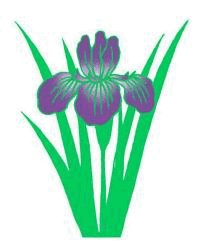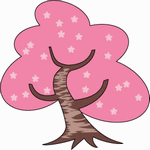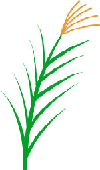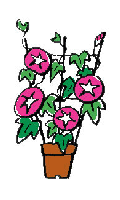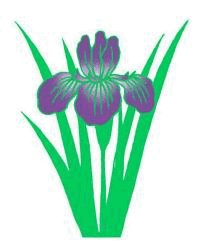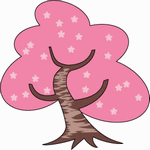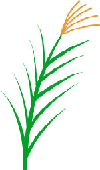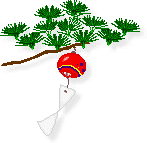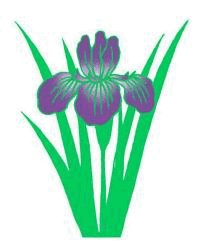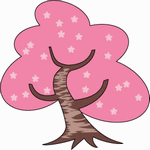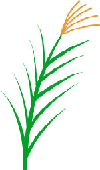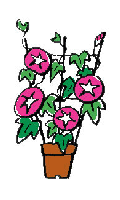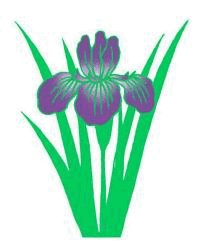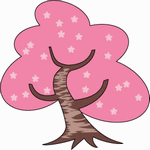2006年から09年掲載分です。
俳句の配列は「櫻草」掲載順です。
同人自選句集「青萍集」所載分は別ページに移しました。
※ 誤字、表記違い等がありましたら、ご連絡ください。

「櫻草」第122號
2009年11・12月號
当季雑詠
| 許されて京の紅葉の宿をとる | 岩渕 如雨
|
| うろこ雲肩書のなき名刺刷る |
|
| 雨に剥く林檎の皮の長さかな |
|
| 声大き客の残せし秋刀魚かな |
|
| 秋雲やたれに別れを告げて来し |
|
| もどかしや栗の実口に入るまで | 奥山 游悦
|
| 洋館をめらめら燃やす蔦紅葉 ○ |
|
| 月の夜人の世を去るかぐや姫 |
|
| ギリシャ史をひたすら学ぶ文化の日 |
|
| 秋桜乙女の仕草風に揺れ ○ | 武蔵 弁慶
|
| うさぎらの童話の世界秋の月 |
|
| 食欲の秋や妻より万歩計 |
|
| 栗の実や世情に叛く子沢山 |
|
| ふるさとの盆地一色稲穂かな |
課題句:小春日、鴨
| 小春日や木漏れ日やさし雑司ヶ谷 | 游 悦
|
| 小春日や羅臼の浜の昆布干し |
|
| 小春日や吾を映せし父母の墓 | 如 雨
|
| 小春日や古書店主人居眠りし | 弁 慶
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 鴨群れて世間話を交わすごと ○ | 游 悦
|
| 鴨翔ちて碧き水紋ひろごりぬ |
|
| 好日や水面を滑るつがひ鴨 ○ | 如 雨
|
| 残照に飛沫残して鴨の陣 ○ |
| 橋の下つがい初鴨ゆつたりと | 弁 慶
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
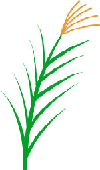
「櫻草」第121號
2009年9・10月號
当季雑詠
| ひと組の客出て夕立止みにけり | 岩渕 如雨
|
| 訥々と語る来し道冷奴 |
| 気懸りな検査前夜の遠花火 |
| 重き荷や白さえも憂し夾竹桃 |
| 独居や二三度立ちて遠花火 |
| ノック受け汗の球児のランニング | 小川 修人
|
| 雲黒くつくつく法師の途切れがち |
| 単線の無人駅舎や夏の月 |
| 禅寺の池に列なす緋鯉かな |
| 菊花展名札はどれも誇らしげ | 奥山 游悦
|
| マンションの灯の数増えて虫の夜 |
| 猫じやらし駄洒落のうまき友のゐて |
| よく見ればそこここにあり残り菊 |
|
| 大海に思ひをつなぐ川泳ぎ | 武蔵 弁慶
|
| 若き日や大志を抱き雲の峰 |
| はまなすや青春の歌知床に |
| 振り下ろす鍬の五つで玉の汗 |
| 江戸切子無色に映える心太 |
課題句:灯火親しむ、柿
| 夜更けまで灯火親しむ千年紀 ○ | 游 悦
|
| 子の寝息灯火親しむ山の宿 | 修 人
|
| 熱き茶に替へて灯火を親しめり | 如 雨
|
| 古稀にして灯火親しむころとなり | 弁 慶
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 屋根伝ひ隣家の柿を食ひし頃 | 修 人
|
| 茅葺の家に被さる柿たわわ |
| 柿剥くや地球のごとく自転させ | 游 悦
|
| 吾にまだ役目あらんか残り柿 |
| ふらふらと柿採る竿の上りけり | 如 雨
|
| 柿植えて三十年で三十個 | 弁 慶
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。

「櫻草」第120號
2009年7・8月號
当季雑詠
| 梅雨空に塔の幾何学模様立ち | 武蔵 弁慶
|
| ほととぎす夢見つ笑ふ赤子かな |
|
| 葉桜や老人一人見つめをり |
|
| 透谷と美那子の出会ひ藤香る |
|
| 合歓眠る朝来し道を戻りけり | 岩渕 如雨
|
| 狛犬の鼻くづれをり新樹蔭 |
|
| 青葉風古き椅子置く停留所 |
|
| 夏痩せて腕には大き時計かな |
|
| 遥かなるダムへの道や朴の花 | 小川 修人
|
| 弟に亡父の面差し夏帽子 |
|
| 不揃ひの吹奏楽や風薫る |
|
| 無人駅通り抜けるや青田風 | 奥山 游悦
|
| 巡航船行く手をはばむ卯浪かな |
|
| 耕運機ひとり働く田植かな |
|
| 川遊び五月の風の通り道 |
|
| 新地下道夏は上野の広小路 | 合田三鬼堂
|
| 道端の草も輝く皐月かな |
|
| 山上の雨乞池は蝌蚪の国 |
|
| 蓮の葉の背伸びしては水面うめ |
課題句:蓮、花火
| 北国の碧空深し蓮の花 | 修 人
|
| 蓮浮葉童子の菩薩遊びゐる |
|
| 蓮の花咲く音聞けり空耳か | 游 悦
|
| 生きぬきし種子の硬さや大賀蓮 | 如 雨
|
| 蓮の花仏のごとく凛と笑む | 弁 慶
|
| 蓮咲いて人待ち顔の蓮見茶屋 | 三鬼堂
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 花火見の心許なき下駄の音 ○ | 如 雨
|
| 手花火や及び腰なる小さな手 |
| 大空に戦仕掛ける花火かな | 游 悦
|
| ビル街の隙間に見ゆる遠花火 |
|
| 連発の後は少し間揚花火 | 修 人
|
| 諸人の心華やか大花火 |
|
| 高層のビルより低き花火かな | 三鬼堂
|
| 遠花火駅々ごとに遠くなり | 弁 慶
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
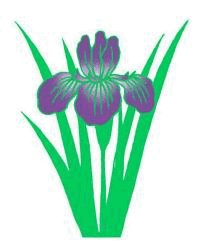
「櫻草」第119號
2009年5・6月號
当季雑詠
| つばくらや古酒醸し出す蔵屋敷 | 武蔵 弁慶
|
| 里山の狐々の声聞き山笑ふ |
|
| 連翹やまぶしいほどの垣根越し |
|
| 採り立ての蕗味噌食ぶる夕餉かな |
|
| 一合の酒あればよし昼蛙 | 岩渕 如雨
|
| 連翹や隣の庭をのぞく癖 |
|
| うららかや猫の目瞑ること幾度 |
|
| 啄木忌裏に声ある等光寺 |
|
| 連翹の思ひの丈の浅黄空 | 小川 修人
|
| それぞれの思ひに揺るる葱坊主 |
|
| 日の当たる空き地恋猫五六匹 |
|
| 徒然の日々を楽しむ朝寝かな |
|
| 南方の魂魄運び初燕 |
|
| 人情の果てを見とほす傘雨の忌 | 奥山 游悦
|
| 湖にほどよくヨット散らばりぬ |
|
| 鯉幟祖父の願ひがひるがへり |
|
| 日本に帰りてうれし青田かな |
|
| ベランダに王者のごとし君子蘭 |
|
| 花あれば花の数ほど歩みけり | 合田三鬼堂
|
| 願いごとうかがい地蔵へ梅雨晴れ間 |
|
| 争いの無き世願ひつ夏は来ぬ |
課題句:更衣、走り梅雨
| 細き娘のますます細き更衣 | 三鬼堂
|
| 樟脳の匂纏ひし更衣 |
|
| いつもやや人に遅れて更衣 | 如 雨
|
| 青白き腕を撫しつつ更衣 |
|
| 姿勢良き少女断髪更衣 | 修 人
|
| 切れ長な双眸清し更衣 |
|
| 更衣生徒の手足生き生きと | 游 悦
|
| 更衣色かはりたる身の軽ろし |
|
| それぞれの人の色した更衣 | 弁 慶
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 庭石のうっすら濡れて走り梅雨 | 游 悦
|
| 走り梅雨気になる空に雲しきり |
|
| 走り梅雨雨垂れ拍子の謡かな | 修 人
|
| 広重の雨は直線走り梅雨 ○ |
|
| 保津川に舟待つ窓や走り梅雨 | 如 雨
|
| 広重の生野を思ふ走り梅雨 ○ | 弁 慶
|
| ワイパーを都電動かす走り梅雨 | 三鬼堂
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
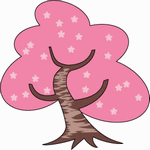
「櫻草」第118號
2009年3・4月號
当季雑詠
| 手袋の中に秘めたる生命線 | 武蔵 弁慶
|
| 年男赤ベコ撫でて初詣 |
|
| 七草や若い命の満ち溢れ |
|
| 鎌倉の老舗を飾る鏡餅 |
|
| 水割のジンの音澄む霜夜かな | 岩渕 如雨
|
| 目の合うて猫の欠伸や去年今年 |
|
| 鐘の音の凍て届きたり古稀の朝 |
|
| まづ晴と日の出の時刻初日記 |
|
| マフラーを厚手に替へて遠き旅 |
|
| 耳澄ませ谿聲聞ゆ木の芽山 | 小川 修人
|
| 庭に生ふ三種を入れて七日粥 |
|
| 冬霞遠き連山昏れにけり |
|
| 身じろぎもせぬ裸木に夕日影 |
|
| 子を抱いてゆるゆる入る初湯かな | 奥山 游悦
|
| 蝋梅の掛花一枝気も新た |
|
| 人の世を深く知りたし西行忌 |
|
| 春眠や果てなき夢に遊びけり |
|
| 鍋焼きの手間と暇かけ味はよし | 合田三鬼堂
|
| 鎖骨折り妻の養生春炬燵 |
|
| 歌舞伎町の鬼は見得切る追儺かな |
|
| 浮世絵師の墓に降りしく桜花 |
課題句:啓蟄、花時
| 啓蟄や蟻の偵察部隊出づ | 修 人
|
| 啓蟄や温もり感ず足の裏 |
|
| 啓蟄や亀寄りあひて甲羅乾す | 三鬼堂
|
| 啓蟄や入れ代はりある社宅かな |
|
| 啓蟄や習ひ始めの一輪車 | 如 雨
|
| 啓蟄や怖ぢけず背伸び発表日 |
|
| 啓蟄の土ほこり舞ふ牛舎かな | 游 悦
|
| 啓蟄や我も出るぞと身構へる | 弁 慶
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 西方は雲の曼陀羅さくらどき | 修 人
|
| 酔ふ人も酔はざる人も花のとき |
|
| 花時の墨田川行く小舟かな | 游 悦
|
| 花時も過ぎて野山は静かなり |
|
| 円空の笑みは優しき花の頃 | 三鬼堂
|
| 花時や妻は憂ひのなきごとし | 如 雨
|
| 人盛る上野の山も花盛り | 弁 慶
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。(今号はなし)

「櫻草」第117號
2009年1・2月號
当季雑詠
| 大空の広きに集ふ秋茜 | 武蔵 弁慶
|
| 短日や農仕事早め切り上げる |
|
| 朔太郎月に吠えての夜寒かな |
|
| 冬日向小吉の籤結びけり | 岩渕 如雨
|
| 文鎮の冷たきを置き摩訶般若 |
|
| 同じやうな咳する男座りけり |
|
| 片付かぬ本に囲まれ風邪籠 |
|
| 青空をぽかりぽつかり雲の輿 | 小川 修人
|
| 往還の木曽の社の薄紅葉 |
|
| 木曽馬の放牧場や紅葉晴 |
|
| 参道を下り来る僧の息白し | 奥山 游悦
|
| おでん屋の暖簾くぐりぬガード下 |
|
| スキーヤーつかず離れず坂下る |
|
| 寄せ鍋に皆の視線が集まりぬ |
|
| 蒼天に蔵王新雪眩しけり |
|
| 野仏の顔を覆いし秋の草 | 合田三鬼堂
|
| カリンの実不揃ひ不揃ひ空に浮く |
|
| 残る福もとめて浅草三ノ酉 |
課題句:初旅、 梅
| 古希迎ふ気分新たに旅はじめ ○ | 修 人
|
| 初旅の古道歩きと寺詣 |
|
| 初旅やなんじやらほいの木曽の宿 ○ |
|
| 初旅や古い鞄も誇らしく | 俊 知
|
| 新幹線晴るれば富士見よ初の旅 |
|
| 初旅はいつものとおりふるさとへ | 弁 慶
|
| 初旅や朝一番の汽車に乗り | 游 悦
|
| 初旅や泳ぎし川の細かりき | 如 雨
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 異国人案内して観る梅の花 | 三鬼堂
|
| 梅枝の路地にはみだす谷中かな ○ |
|
| 梅咲いて何怒りしか忘れたり | 如 雨
|
| 梅一輪百花に適ふ忌明けかな ○ |
|
| 神さびて吾にほころぶ臥龍梅 | 修 人
|
| 青空に枝先溶ける野梅かな ○ |
|
| 梅もげば青春の香の匂ひけり | 弁 慶
|
| 梅園やいずれの梅の香りやら | 游 悦
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。

「櫻草」第116號
2008年11・12月號
当季雑詠
| 秋刀魚焼き春夫の詩を口遊む | 武蔵 弁慶
|
| ふるさとの新涼求めバスに乗る |
|
| 連山を望みて里の柿簾 |
| 朝顔や千代の心を思ひけり |
|
| 子規庵の糸瓜八本ぶらさがり |
|
| 忘れてもよきこと多し秋入日 | 岩渕 如雨
|
| 萍の吹かれし面や秋の雲 |
|
| 啄木の寝転びし城草紅葉 |
|
| 秋の湖腹を曝せしボートかな |
|
| 谿聲に耳傾くる紅葉酒 | 小川 修人
|
| 志ある句を詠まん天高し |
|
| 才人の畏友は逝けり曼珠沙華 |
|
| 単線の終着駅は曼珠沙華 |
|
| 歳時記に押し葉となりて草じらみ |
|
| 高層を競ふマンション鰯雲 | 奥山 游悦
|
| 足の向く気の向くままの紅葉狩 |
|
| 新しき歳時記買ひぬ文化の日 |
|
| わが住まひ熱燗のほか友いらず |
|
| 漱石忌我が才能の貧しさよ |
|
| 秋冷や朝日の影に背を伸ばす | 合田三鬼堂
|
| 秋晴や大川のぼるはしけかな |
|
| ボール打つテニスコートや山装ふ |
|
| 天候の不順に耐へし糸瓜かな |
|
| いつの間に庭に住み居る彼岸花 |
課題句:冬木立、山眠る
| 北限の野猿は哀し冬木立 ○ |
三鬼堂
|
| 間伐かチェーンソー鳴る冬木立 | 修 人
|
| こんもりと淡き墨絵の冬木立 | 游 悦
|
| 大空に出番を待てる冬木立 | 弁 慶
|
| 冬木立影入り交はし夕日去る | 如 雨
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 山眠る杉も立ちゐて眠りけり ○ |
如 雨
|
| 山眠る往古の夢を手繰りてむ |
| 諦めにあらず達観山眠る | 修 人
|
| 人の世のことはさておき山眠る |
|
| 天空に月はたたずみ山眠る | 三鬼堂
|
| 山城の天守も山も眠り居て |
|
| 山眠る妻のひとこと発奮す | 弁 慶
|
| 借景の山も寺院も眠りけり |
|
| 猟銃の音谺せり山眠る | 游 悦
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
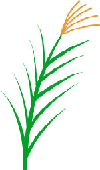
「櫻草」第115號
2008年9・10月號
当季雑詠
| 薬師寺に平癒祈りし夏の雨 | 合田三鬼堂 |
| 花火師の技を競うや隅田川 | (俊知改め)
|
| 胸突坂へ脚の震える大暑かな |
|
| 朝顔へ半纏水やる入谷かな |
|
| 弱き我英気いただく雲の峰 | 武蔵 弁慶
|
| 雲の峰天地有情の境地なり |
|
| 修験道法螺貝吹きて雲の峰 |
|
| 夏痩せの妻畑作に精を出し |
|
| まとひつく蜘蛛の囲はらひ剪定す |
|
| 迎火や大徳利を選りてきし | 岩渕 如雨
|
| 紅させばそれにて佳人花浴衣 |
|
| ただいまと言へど主なき立葵 |
|
| 日昇りて乾かぬ翅の蝉動く |
|
| 御湿りの去りて忽ち蝉時雨 | 小川 修人
|
| 声大き球児の背に雲の峰 |
|
| 馬鈴薯の花の果てなる地平線 |
|
| 難病の指定受けたり青ぶだう |
|
| 北の果てコスモス揺れる浜辺かな | 奥山 游悦
|
| 水澄みてゆらりと動く魚影かな |
|
| 鳥翔ちてななかまどの実残しけり |
|
| 笛の音のもの悲しきや秋祭 |
課題句:野分、秋の山
| 野分過ぐ骨折れ傘の散らかりて | 三鬼堂
|
| 公園に干物をみる野分晴 | (俊知改め)
|
| 野分去り増へたる星の名を問はる | 如 雨
|
| 開港の絵飾る店や野分立つ |
|
| 風天の一日天下野分かな | 修 人
|
| 嵯峨野原かなしく吹ける野分かな | 弁 慶
|
| 廃屋の壁剥がれをり野分かな | 游 悦
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 空澄みて声も澄みたり秋の山 ○ | 游 悦
|
| 人影のなき秋嶺をはしいまま |
|
| 秋山や雨より早く雨の音 ○ | 如 雨
|
| 山粧ひ出湯は染まる湯治かな | 三鬼堂
|
| 淋しさを覆ひ隠せよ秋の山 | 修 人
|
| 磐梯の噴火の跡に山粧ふ | 弁 慶
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
なお、谿聲主宰病臥のため前114号から当季雑詠の ○ 印 はありません。
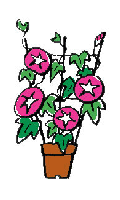
「櫻草」第114號
2008年7・8月號
当季雑詠
| いろいろなものまとひつき梅雨に入る | 岩渕 如雨
|
| 鬼灯のふたつ赤むを買ひてきし |
|
| 半年の無沙汰の筆の夏書かな |
|
| 父が植ゑ母も好みし立葵 |
|
| 籐椅子の軋みて父の十年忌 |
|
| ががんぽや我も余光の日を送る | 小川 修人
|
| 此所彼所煩悩無尽女郎蜘蛛 |
|
| 華やげど忽ち消ゆる揚羽かな |
|
| 煩悩をこぼして舞へり夏の蝶 |
|
| この世には憂ひの無きか熊ん蜂 |
|
| お茶会を終へし嬋娟つつじ咲く | 奥山 游悦
|
| そこここに客かたまりて川開き |
|
| 波乗りの若者白き歯を見せて |
|
| 尾根伝い転々と行く登山帽 |
|
| ブルージュの春風切って馬車走る |
|
| 下北の緑は浅き五月かな | 合田 俊知
|
| 巡礼の喉を潤す岩清水 |
|
| 道祖神のほおかぶりするやませかな |
|
| 恐山の夏風すぐる地蔵堂 |
|
| やませ吹く人みな無口網手入れ |
|
| 継之助傷つき辿る桐の花 | 武蔵 弁慶
|
| 実盛の兜に涙芭蕉かな |
|
| 苦界避け池に潜むか昼蛙 |
|
| 今の世に何を願ふか武者人形 |
|
| 武者人形矮小にして勇ましく |
課題句:雷、蜩
| 大仏は泰然自若雷去りぬ ○ | 修 人
|
| 雷神も恋ふらん豊頬吉祥天 |
|
| 雷を退散させる仁王かな ○ |
|
| 迅雷の送り迎えや上州路 ○ | 俊 知
|
| 遠雷は旅人急かす峠越え ○ |
|
| 雷の宗達の威を借りしかな ○ | 弁 慶
|
| いきなりの雷鳴街は震えたり | 游 悦
|
| 雷恐る卒壽の母のそら笑ひ | 如 雨
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| ひぐらしや巡礼山門一礼す | 俊 知
|
| ひぐらしに和尚の戻る古刹かな | 俊 知
|
| 蜩や応援の声なほ高く ○ | 如 雨
|
| 転寝や風の連れ来し遠ひぐらし |
| かなかなの輪唱続く日暮かな | 修 人
|
| 蜩の王国ならん雑木山 |
|
| かなかなや生きる哀しみ伝へをり | 游 悦
|
| 蜩や宿題の山片付かず | 弁 慶
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
なお、谿聲主宰病臥のため今号から当季雑詠の ○ 印 はありません。
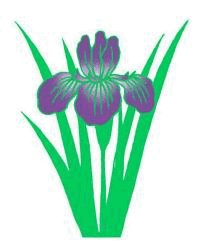
「櫻草」第113號
2008年5・6月號
当季雑詠
| 来るたびに孫の重さや鯉幟 ○ | 奥山 游悦
|
| 春惜しむ青春惜しむ世を惜しむ |
|
| 老妻が童女に還る磯遊び |
|
| 兄逝きて間遠となりし帰省かな |
|
| 手術終へ目に沁み入るや夏芝生 |
|
| 碧梧桐自筆の墓標梅香る ○ | 小川 修人
|
| 未来への仄かな希望春の星 |
|
| アネモネや妖精たちの栖む処 |
|
| 空色はわがためなるぞ犬ふぐり |
|
| 横丁の春泥避けて猫の道 |
|
| 鳥過ぎる影の速さよ春あした | 岩渕 如雨
|
| 瞬きてそこに生まれし春の海 |
|
| 言ひ合ひて缶蹴り帰る一年生 |
|
| 読経終へ僧の語るや堂ぬくし |
|
| 海棠や誰か誉めさう稚児化粧 |
|
| 町並に映えて谷中の櫻かな | 合田 俊知
|
| 業平の駅に集ひし花見客 |
|
| 隅田川川面を埋めし花見舟 |
|
| 老舗湯屋閉づるを惜しむ春の雨 |
|
| 庭師入り巣箱露や春の庭 |
|
| 冬晴れやどこまで伸びるクレーン塔 | 武蔵 弁慶
|
| 雪降つて景となりたる狭庭かな |
|
| 西側の屋根に残雪留まれり |
|
| 株下がりなすべき手なし余寒かな |
課題句:短夜、鮎
| 明易や雲従へて山座る | 如 雨
|
| 短夜や雨かと覚めぬ川の宿 |
|
| 明急ぐ帳の隙に陽の光 | 俊 知
|
| 短夜や釣り宿客の慌し |
|
| 亡き友と夢幻語らふ短夜かな ○ | 修 人
|
| 短夜や異国の宿で句友識る | 游 悦
|
| 短夜やストレス多く眠られず | 弁 慶
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 夕星や姿良き鮎串にあり | 修 人
|
| 北限の鮎鮓美し余市川 ○ |
|
| 釣人の鮎はむ岩を究めけり ○ | 俊 知
|
| 塩振らる鮎の目さらに激しかる | 如 雨
|
| 床の間の渓流の中鮎泳ぐ | 弁 慶
|
| 水みどり釣られし鮎の白き腹 | 游 悦
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
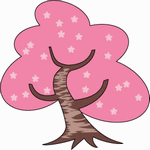
「櫻草」第112號
2008年3・4月號
当季雑詠
| 若水の湧きくるところ井之頭 ○ | 合田 俊知
|
| 門前に琴の音流す初薬師 |
|
| ひろき道迷い出でたる寒念仏 |
|
| 治郎吉の墓石削らる入試かな |
|
| 鳥帰る別れを惜しむ都鳥 |
|
| 手鏡に紅なほす巫女息白し ○ | 岩渕 如雨
|
| 瞑りゐて故郷過ぎる初湯かな |
|
| 故郷の神札(は残して札納 |
|
| 詠みあぐね頬杖多き三日かな |
|
| 土混じり野うさぎとなる今朝の雪 |
|
| 激動の年のシンボル嫁が君 ○ | 武蔵 弁慶
|
| 初春や神田古書店客ひとり |
|
| 神さびる巫女より受くる破魔矢かな |
|
| 良寛の座禅せし寺初明り |
|
| 朝よりの初湯上がりてすがすがし |
|
| 流氷の港に青き船の道 ○ | 小川 修人
|
| 寒明けて噴火のごとく杉花粉 |
|
| 水仙の一叢路地に日の恵み |
|
| この先は夢幻泡影雪女 |
|
| 虚子一途悔しさ消えず久女の忌 |
|
| 春眠に吸い込まれけり妻の声 | 奥山 游悦
|
| 天空に変幻自在揚雲雀 |
|
| 啓蟄や植木鉢にも芽を凝らす |
|
| 棒切れに蝌蚪の紐下げ児らはしゃぎ |
課題句:雛祭、朧
| 雛祭朝のあいさつ歯切れ良き | 如 雨
|
| ひな飾る家らし子らの歌ふ声 ○ |
|
| 相模灘風も優しき吊し雛 | 俊 知
|
| 下校の子手に手に千代の雛を持ち ○ |
|
| おしゃべりな孫とおはじきひなまつり | 修 人
|
| 浅草の老舗古雛飾りけり | 弁 慶
|
| 紙雛を孫に送りて便り待つ | 游 悦
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 初恋の人は去りゆく朧かな | 俊 知
|
| 不忍の鳥は眠りし朧かな ○ |
|
| 水煙の空に溶けゆく朧かな ○ |
|
| 主なき庭のミモザの花おぼろ ○ | 游 悦
|
| 朝まだき夢うつつなる鐘おぼろ ○ |
|
| 群れをなしおぼろの山へ夕烏 ○ | 修 人
|
| 朧夜の一本道を我ひとり | 如 雨
|
| 露天風呂入りてひとりの朧かな | 弁 慶
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。

「櫻草」第111號
2008年1・2月號
当季雑詠
| 芝居はね盃かさね走り蕎麦 | 合田 俊知
|
| 外堀の桜紅葉や電車往く |
|
| 銀杏散る人へ車へ銀杏散る |
|
| 身代りの地蔵尊あり寒の雨 |
|
| 石蕗の隠れ咲きゐる小路かな |
|
| 登り来て年寄り自慢秋日和 | 岩渕 如雨
|
| 城跡の夢の先なる蔦紅葉 |
|
| 散り急ぐ桜紅葉や川走る |
|
| 黙祷に始まる集ひ冬隣 |
|
| 襟首を木枯一号山光る |
|
| 柿たわわ空は青きを増しにけり | 小川 修人
|
| 校庭に理科観察の稲稔る |
|
| 落葉掻く慈顔碧眼修行僧 |
|
| 頭垂れ警策愛くる鵙日和 |
|
| 新米を仙台味噌と味はへり | 武蔵 弁慶
|
| 狛犬に見守りまかせ神の留守 |
|
| 剪定の終わりし庭に添水かな |
|
| 秋灯火丸山真男再読す |
課題句:筆始、蕗の薹
| 鬼城の書座右に置きて筆始 | 俊 知
|
| 書初は寿一字の齢かな |
|
| 傍らにぐい飲み置きて筆始 ○ | 修 人
|
| 勢ひのある一文字の筆始 | 如 雨
|
| 平凡と非凡境地で筆始 | 弁 慶
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| ガリ刷りの文集出でぬ蕗の薹 | 如 雨
|
| これいかが暖簾収めて蕗の薹 |
|
| 六地蔵在す路辺に蕗の薹 | 修 人
|
| なほ尖る風にふくらむふきのとう |
|
| 市ヶ谷の蕗の薹みるお堀かな | 俊 知
|
| 近道と千鳥ケ淵や蕗の薹 |
|
| 蕗の薹土の気孕み出でにけり | 弁 慶
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。

「櫻草」第110號
2007年11・12月號
当季雑詠
| 地の熱を天に吐き出す百日紅 ○ | 小川 修人
|
| 蒼天に秋風颯颯ちぎれ雲 |
|
| いつまでも終らぬ記憶原爆忌 |
|
| 仰向けに蟻と戦ふかなぶんぶん |
|
| 熱波去り日暮とともに虫時雨 |
|
| 秋の蚊の生の一念我を刺す | 岩渕 如雨
|
| 秋の蝶駅の花屋の鉢に舞ふ |
|
| 敬老の日も飲み慣れし酒一合 |
|
| 窓わづか開け蟋蟀と幾ときか |
|
| かすかなる風のあるらし蕎麦の花 |
|
| 踊り手の大地踏み締む秋祭 | 合田 俊知
|
| 秋の陽や招き猫のみ豪徳寺 |
|
| 集団の自決めぐりて秋深し |
|
| すき焼きに明治の味みる湯島かな |
|
| ふるさとの風に波打つすすきかな | 武蔵 弁慶
|
| 外風呂に入りてひとりの残暑かな |
|
| 好色の言葉消えたり西鶴忌 |
|
| ふるさとの芒茫々生ひ茂り |
課題句:目貼、一茶忌
| 大層な仕事せしごと目貼終ふ | 如 雨
|
| 古民家にかすかに残る目貼かな | 弁 慶
|
| 疎開せし頃の思ひ出目貼かな | 修 人
|
| 姉兄の母を手伝う目貼かな | 俊 知
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 床の間の蛙正座や一茶の忌 ○ | 俊 知
|
| 描かれし人物まろき一茶の忌 |
|
| 古里の家に父母なし一茶の忌 | 如 雨
|
| 露の世に齢重ねて一茶の忌 ○ |
|
| 一茶忌や屋号こばやし走り蕎麦 | 修 人
|
| 一茶忌や月と仏の信濃人 |
|
| 不遇ゆゑ秀句生み出し一茶の忌 | 弁 慶
|
| |
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
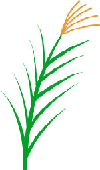
「櫻草」第109號
2007年9・10月號
当季雑詠
| 山門の内なる霊気凉けれ ○ | 小川 修人
|
| 花擬宝珠うすむらさきの雨含む |
|
| 梅雨晴や白線新た草野球 |
|
| 滝落つる光のしぶき一直線 |
|
| 青畳大の字となる大暑かな |
|
| 意見され反論できず滲む汗 ○ | 武蔵 弁慶
|
| 愛蔵の竣介絵売り新茶飲む |
|
| 夕立に広重生野思ひけり |
|
| 調べもの一日ひとり梅雨ごもり |
|
| 老人の迷子アナウンス夏の宵 |
|
| 垂るる穂の毫も動かぬ暑さかな | 岩渕 如雨
|
| 啄木の墓はまなすの残り花 |
|
| 花火果つ宴の声のなほ高く |
|
| 幼児の箸には難し心太 |
|
| 空席の増えし列車や遠花火 |
|
| 世事疎き我の好みや心太 | 合田 俊知
|
| 梅雨空や別れもありし神楽坂 |
|
| 石仏を洗ふ根岸や水凉し |
|
| 打ち水の古き路地ある下谷かな |
|
| 弁天堂囲みて広き蓮華かな |
課題句:震災忌、湿地
| 老猫の大きく伸びて震災忌 | 如 雨
|
| 大川の蕉翁潤むや震災忌 |
|
| 下町を漫ろ歩くや震災忌 | 修 人
|
| 雑踏の一人でありぬ震災忌 |
|
| 天災の後は戦災震災忌 |
|
| 震災忌写真に見入る慰霊塔 | 俊 知
|
| 幅広き昭和通りや震災忌 |
|
| 幼い日夜空にグラマン戦災忌 | 弁 慶
|
| 幼い日大人が泣いた終戦日 |
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| いでわれも湿地の山に分け入らむ ○ | 修 人
|
| ふるさとの縄手通りに湿地売り ○ |
|
| 湿地生ふる山にてありし新開地 ○ | 如 雨
|
| はらからの揃ひし膳に湿地かな |
|
| 鍋に入りなほ丈競ふ湿地かな |
|
| 鳥うちの腰にさげたるしめぢかな | 俊 知
|
| 森林の英気で育つ湿地かな | 弁 慶
|
| 冷や酒の通しに匂ふ湿地かな |
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
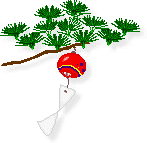
「櫻草」第108號
2007年7・8月號
当季雑詠
| 鮒鯉も川鵜も昼寝の烏川 ○ | 合田 俊知
|
| 菅公の産湯の井戸や枇杷実る |
|
| 加茂茄子は若冲生地に売られけり |
|
| 貴船川式部の恋路青楓 |
|
| 貴船川そうめん流す葦簾蔭 |
|
| 青柿の落つや職退く時と知る ○ | 岩渕 如雨
|
| 伐りし木に冠のごと柿若葉 |
|
| 驟雨きて僧足早に永平寺 |
|
| 白髪の抱ふる薔薇や深夜バス |
|
| 早々に猫の昼寝の場所決まる |
|
| 更衣天の香具山思ひけり ○ | 武蔵 弁慶
|
| 鰐口の首響きけり春の宵 |
|
| 豪商の白壁朽ちて春の雨 |
|
| 磐梯の真白き峰や春の風 |
|
| 円仁の偉業を辿るつつじ道 |
|
| 草茂る三叉路に佇つ道祖神 | 小川 修人
|
| 遠雷に奥歯の疼く夜更かな |
|
| 田水沸く路辺に石の大黒天 |
|
| 切れ長におはす大仏風薫る |
|
| 三伏や大仏の背は開かれて |
課題句:夏館、七夕
| 猫のやうに通り抜けたし夏館 | 如 雨
|
| 雨あがる蔦の窓開く夏館 ○ |
|
| 夏館ふくらむ雲の濃さ淡さ |
|
| 夏館楡の木蔭に微睡めば | 修 人
|
| 風とともに去りぬ青春夏館 |
|
| あけはなし世俗すてたる夏館 | 俊 知
|
| 庭に出て水琴窟聴く夏館 |
|
| 武家屋敷風の素通り夏館 | 弁 慶
|
| 禅寺の坐禅道場夏館 |
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| みちのくの雨に二星の逢瀬かな ○ | 如 雨
|
| それぞれに傘傾げゆく星祭 ○ |
|
| 七夕や星座をふたつ知りしころ |
|
| みちのくや七夕飾りにからくりも | 俊 知
|
| 商人の意気は七夕飾りかな |
|
| わが学都七夕まつりなつかしき | 弁 慶
|
| 仙台の七夕かざり軽やかに |
|
| 軒に吊す七夕人形わが故郷 | 修 人
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
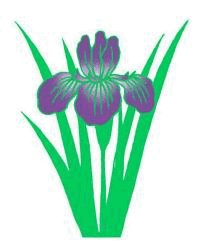
「櫻草」第107號
2007年5・6月號
当季雑詠
| 忘れゐしピースの香り啄木忌 ○ | 岩渕 如雨
|
| ひこばえや横断歩道を子ら走る |
|
| 海棠の蘂に葺かれし小灯籠 |
|
| 相客も同じ蕎麦にて花の酒 |
|
| 静もれる板戸の家や花辛夷 |
|
| 弥陀仏の慈悲に笑むやう白牡丹 ○ | 小川 修人
|
| たそがれて処々に水紋残る鴨 |
|
| 麦秋やゴッホ兄弟眠る丘 |
|
| 鉄線花大慈大悲の風に和す |
|
| 海棠の揺るるは貴妃の笑むごとし |
|
| 勝浦や六十段の雛飾 | 合田 俊知
|
| 心せく都踊や京の春 |
|
| 花満ちる社に祈る三姉妹 |
|
| 花人となりて忘れる足の萎え |
|
| 雪解けの水のささやくひとりごと ○ | 武蔵 弁慶
|
| 春愁や外出に財布をまた忘れ |
|
| 蒲公英や凛然とした母思ふ |
|
| 縁の下大声上げる猫の恋 |
課題句:カーネーション、鯰
| カーネーションの赤を選びぬ百カ日 ○ | 如 雨
|
| はらからの名並べ白きカーネーション |
|
| 幼きが気取り顔してカーネーション | 修 人
|
| 食卓のカーネーションに朝の風 |
|
| カーネーション送りたき母今はなし | 弁 慶
|
| 明るきは歩道を飾るカーネーション | 俊 知
|
| カーネーション飾りし日比谷花の店 |
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 梅雨鯰腹に蛙を入れたるか | 修 人
|
| その名より味は淡白鯰鍋 |
|
| ざんざ降る野川の主ぞ大鯰 |
|
| 釣り上げし鯰静かや魚籠のなか | 俊 知
|
| 鯰焼く肉の白さや膳の上 |
|
| 針呑みてなほ悠悠と鯰かな | 如 雨
|
| 鯰の実白きマシュマロ思ひけり | 弁 慶
|
○印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
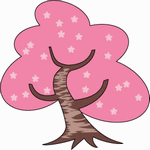
「櫻草」第106號
2007年3・4月號
当季雑詠
| 食積の母につながる妻の味 ○ | 小川 修人
|
| かたまりて和気藹々の福寿草 |
|
| 残月の艶なる空につばくらめ |
|
| 日向ぼこ子犬の足の太さかな |
|
| たたなはる山並おぼろ里の灯も |
|
| 晴無風よき年ならむ初日記 ○ | 岩渕 如雨
|
| 星がみな大きくなりぬ霜夜かな |
|
| 七日粥母の流儀でつくりけり |
|
| 嗄れし声を競ふや年の市 |
|
| 三日はや戸を閉づ無住の社かな |
|
| 遠富士を描き出したる初日かな | 合田 俊知
|
| 寒行の団扇太鼓や坂の街 |
|
| 大寒や日溜りを行く黒き猫 |
|
| 佳人来て指折り数ふ梅の園 |
|
| 文豪の俳句濫觴漱石忌 ○ | 武蔵 弁慶
|
| 権現が起源の庵水仙花 |
|
| 雪なくて雪囲とは淋しけれ |
|
| 初空にくっきり富士の綿帽子 |
課題句:五加木、春暁
| ほろ苦き想ひさておき五加木飯 | 修 人
|
| 手の甲を五加木に掻かれ庭手入れ |
|
| 旅人の五加木てんぷら愛でにけり | 俊 知
|
| 嬰嬰泣けば風なくも落つ五加木花 | 如 雨
|
| 嬰嬰泣くやおもちゃのやうな五加木花 |
|
| 菜飯食べ幼いときの母思ふ | 弁 慶
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 春暁の雲間に浄土垣間見る ○ | 修 人
|
| 春暁や低く旋回鳩の群 ○ |
|
| 春暁や小公園の太極拳 |
|
| 春暁は枕草子の世界たり ○ | 弁 慶
|
| 春暁に清少納言を思ひけり |
|
| 春暁や通知待つ日の茶の柱 | 如 雨
|
| 春暁や眠たき犬の曳かれをり |
|
| 春暁や急がぬ旅の早目覚め |
|
| 大川に繋船眠る春曙かな | 俊 知
|
| 春暁や観音すでに目覚めけり |
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。

「櫻草」第105號
2007年1・2月號
当季雑詠
| 柿吊す母屋に響くジャズピアノ ○ | 小川 修人
|
| 落城の主従の墓に野紺菊 |
|
| 飛び飛びの休耕田に泡立草 |
|
| 鉦叩き枕の合はぬ旅寝かな |
|
| しぐるるや波音とどく露天風呂 |
|
| 宿場跡路傍に蜜柑の実るのみ | 合田 俊知
|
| 両国や初場所看板歳の暮 |
|
| 竹本のいろは送りや歳終る |
|
| 歳時記の電池新たに歳の暮 |
|
| 石割の桜もみじに日照雨かな | 岩渕 如雨
|
| 夕日きてこがね色濃き晩稲かな |
|
| 茅屋根の苔光りをる夜寒かな |
|
| 陽だまりに茶喫む庭師や冬構 |
|
| 山小屋の冬眠告ぐる釘の音 ○ | 武蔵 弁慶
|
| ふるさとの景となりたる冬囲 |
|
| 今年また溝に咲きたる秋桜 |
課題句:寒卵、麦踏
| 老鶏のくぐもる声や寒卵 ○ | 如 雨
|
| 寒卵粥の真中に埋もれけり |
|
| 朝膳や碾割り納豆寒卵 | 俊 知
|
| 寒卵特売とせり野菜売り |
|
| 安曇野の思い出話寒卵 | 修 人
|
| 留守番の一膳飯や寒卵 |
|
| 朝食の日の出のような寒卵 | 弁 慶
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 後ろ手に麦踏む人の影法師 ○ | 修 人
|
| 麦踏や段々畑下りつつ |
|
| 麦踏や裾野の長き赤城山 |
|
| 麦踏の影直角に畦を切る ○ | 如 雨
|
| 子の足に余る地下足袋麦を踏む |
|
| 麦踏にミレー晩鐘思ひけり ○ | 弁 慶
|
| 麦を踏む親の真似する頬被り | 俊 知
|
| 麦踏むや麦の強さの一筋に |
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。

「櫻草」第104號
2006年11・12月號
| 秋めくや夏の歳時記繕ひぬ | 合田 俊知
|
| 虫の音を聞きつつ楽堂開くを待つ |
|
| 能楽堂出づれば虫鳴く現世かな |
|
| 役者寺まず出迎へし酔芙蓉 |
|
| ふるさとのもろこしかたきよはいかな |
|
| あめつちの虚実の間を虫時雨 | 小川 修人
|
| 稚児落し故事ある懸崖照紅葉 |
|
| 頂上や八方世界霧の中 |
|
| 枯枝に嗄れ鴉の地獄谷 |
|
| ここ連夜雨に負けじと虫すだく |
|
| 玄関に淋しく残る茄子の馬 | 武蔵 弁慶
|
| 庭園の池をするする行く小鴨 |
|
| 大根の味噌汁うまし妻の味 |
|
| 山柿の夕日の映ゆる朱色かな |
|
| 山小屋の冬眠間近し雪囲 |
|
| そろそろと煙塊来り花火尽く | 岩渕如雨
|
| 放生の野にすっきりと曼珠沙華 |
|
| 門閉づや園児の植ゑし夕化粧 |
|
| 風よしと書けば忽ち残暑来る |
|
| 道暗む下駄は苦手の浴衣かな |
|
| 蕎麦の花分け入る先は祖師の寺 | 平山 隆一
|
| 萩やさし故郷の人の玉日講 |
|
| 彼岸花護摩焚く僧を加勢せり |
課題句:泥鰌掘る、
鳰
| どぢやう掘つて泥ごともどる主人かな ○
| 俊 知
|
| どぢやう掘る白き手拭ひほほかむり |
|
| 安曇野に風吹き下す泥鰌掘り ○ | 修 人
|
| 泥鰌掘る子供の頃の青つ洟 |
|
| 掘りだせばかなしき声のどぢやうかな ○ | 如 雨
|
| 甲高き声に交じりて泥鰌掘る |
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 星影の湖に浮寝か鳰 ○ | 修 人
|
| 倒木の野川をすいと鳰 ○ |
|
| 鈍色の波間を潜る鳰 |
|
| ひた潜る鳰の波紋やはづれ岸 ○ | 如 雨
|
| 潜る親惑ひて追ふや鳰のひな |
|
| かいつぶり潜りて湖面静かなり | 俊 知
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
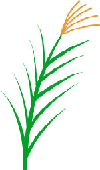
「櫻草」第103號
2006年9・10月號
当季雑詠
| 職退きて親しむ水絵梅雨もよし ○ | 岩渕 如雨
|
| 水すまし何年ぶりの出会ひかな |
|
| 木道や花まで遠き大賀蓮 |
|
| 少年の吾にふと会ふ夏の海 |
|
| 夏の波ささめ言して去りにけり |
|
| 旅にゐて辛子のきゝし心太 ○ | 小川 修人
|
| 涼風や湿原蛇行釧路川 |
|
| 夏霧にペンションの村見え隠れ |
|
| 夕涼や土を浴びゐる烏二羽 |
|
| 郭公の木霊となりぬ奥社 |
|
| 立ち退きの空き地に神酒所秋祭 ○ | 合田 俊知
|
| 長梅雨に人影絶えし社かな |
|
| 琉金の泡が一つ二つ三つ |
|
| 阿波踊佳き女踊る神楽坂 |
|
| 御朱印に紅葉栞るや中尊寺 |
|
| 蒼天に郭公の声澄みわたる | 武蔵 弁慶
|
| 豪雨去り路面清涼夏の朝 |
|
| 栗の花雀が一羽遊びけり |
|
| 不二の峰背負ひて夏の波見たり |
課題句:鬼城忌、通草
| 鬼城忌や昔はここに揚げ雲雀 ○ | 如 雨
|
| 鬼城忌や赤城は大き雲を置き ○ |
|
| 鬼城忌や入り日幾条山を射る |
|
| 鬼城忌に上毛三山鎮まれり | 修 人
|
| 鬼城忌や老手青畝も聾なりし ○ |
|
| 鬼城忌や心に沁みる句を得たし |
|
| 高崎の町並変はりし鬼城の忌 | 俊 知
|
| 俳諧の王道のなし鬼城の忌 | 弁 慶
|
| 俳諧の王道けわし鬼城の忌 |
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 山主も知らず通草の熟れし時 ○ | 如 雨
|
| 通草蔓手繰りて実なき猿の山 |
|
| 熟れあけび通草細工の籠に盛る ○ | 修 人
|
| 甘きものなき頃思ひあけび食ふ ○ |
|
| 頬張りてあけびの種を飛ばさんか |
|
| 目籠隅通草も入るる山の幸 ○ | 俊 知
|
| 故郷の山は通草の甘さかな ○ |
|
| 幼き日友と食べにし通草かな | 弁 慶
|
| それぞれの森の色した通草かな |
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
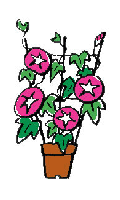
「櫻草」第102號
2006年7・8月號
当季雑詠
| 古祠幕張るのみの祭かな ○ | 岩渕 如雨
|
| 羊歯に拠り小さき蜥蜴の驚かず |
|
| 日当たりを避けて歩くや啄木忌 |
|
| 田植機の千往復の青田かな |
|
| どくだみを残し十字の白を愛づ |
|
| 緩る緩ると初夏の旅する八高線 ○ | 小川 修人
|
| 正客の凛と帯締む杜若 |
|
| ハンモックトムソーヤの気分かな |
|
| 乱れ打つ太鼓の稽古祭前 |
|
| 苺摘む幼子吾を振り返る |
|
| 俳画かく墨の香はこぶ初夏の風 | 合田 俊知
|
| 山桐の花誇らしげ元助碑 |
|
| 夏草や俳書へいざなふ風知草 |
|
| 文学の湖へ青鷺ただ一羽 |
|
| 最上川芭蕉が拝む滝流れ | 武蔵 弁慶
|
| 不二の峰背負いて夏の波寄する |
|
| 実朝や沖の小島に夏の波 |
|
| 水牢で死しはまことか人麿忌 |
課題句:硯洗ひ、梅干
|
硯洗ふ明夜の晴れを願いつつ ○ | 俊 知
|
| 我が願ひ恥ずかしくもあり硯洗ふ ○ |
|
| 洗ひたる硯に願ふ夢淡し ○ | 修 人
|
| 洗ひたる硯に残る墨の澱 |
|
| 硯洗ふ去年の願ひをまた書かむ ○ | 如 雨
|
| 硯洗ふ小筆の穂先検めつ |
|
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 朴の葉の影深まりて梅干しぬ | 修 人
|
| 庭に生る不揃ひの梅干しにけり ○ |
|
| 梅干すやすずめ筵をめぐるのみ | 如 雨
|
| 梅干すや三和土に黒き汁の壷 |
|
| 梅漬けに里の香りを偲びゐる | 俊 知
|
| 梅干の器あらため朝の膳 |
|
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
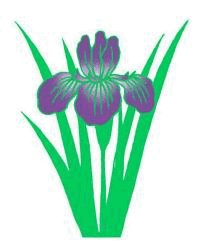
「櫻草」第101號
2006年5・6月號
当季雑詠
| じゃがいもの花の麓や羊蹄山 ○ | 小川 修人 |
| 夏座敷我が物顔に猫通る |
| 忘れたき過ぎし日々ある安居かな |
| 行き違ふ夫婦の会話夏燕 |
| 花人に門大開す芭蕉庵 | 合田 俊知 |
| 鴎外の庭の彩り花馬酔木 |
| 連隊の記憶は花の中となり |
| 帰り来るところは一つ花の路 |
| 芽柳や校正係啄木碑 | 岩渕 如雨 |
| 春一番四十年の疾きかな |
| 詠みさして梅訪ふ鳥の声を待つ |
| 三日後は桃花と笑むや紺がすり |
| 不摂生をくやむ日々なり春の風邪 | 武蔵 弁慶 |
| 夏めきて軽く登りし化粧坂 | |
| この一日すべて捨て去るさくらかな |
| 長谷寺のかいどう紅神々し |
課題句:篠の子、黴
| 分け入って篠の子取か山頭火 ○ | 修 人 |
| 篠の子や神仙降りる沼ありぬ ○ |
| 篠の子のゑぐみ味はふ煮しめかな |
| 篠の子を避けて荷をおく登山帽 | 如 雨 |
| 篠の子のとんがり留守の椀にあり |
| 篠の子の育ち気になる隠し山 ○ | 俊 知 |
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 思ふやう事は運ばず黴の宿 | 修 人 |
| 未だ開けぬボルドーの壜黴にけり |
| 若き日の愛読の書は黴にけり | 俊 知 |
| 黴拭きぬ神秘の力採るごとく | 如 雨 |
| 去りし子や部屋にひとすじ黴歩く |
| 上古(なる壁画の色を盗りし黴 ○ |
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
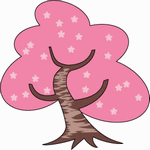
「櫻草」第100號
2006年3・4月號
当季雑詠
| 客一つ役者も一つ歳をとり | 合田 俊知 |
| 寒椿一輪手折る女かな |
| ビル出でて花降りかかる喫煙所 |
| 山城屋贔屓袢纏初芝居 |
| 雪解川廃坑多き空知かな | 小川 修人 |
| たんぽぽや工場跡の赤煉瓦 |
| 愛用の碁盤に立てる雛かな |
| 顔見せぬ子にメール打つ雛祭 |
課題句:雉、桜餅
| 大仏の背負ひし山や雉子のほろろ ○ | 俊 知 |
| 雉子遊ぶ山裾近き庵かな ○ | |
| 北斎の雉子上目にて睨みたる | 修 人 |
| 雉子鳴かむ山の中なる住宅地 | |
| ‥‥‥‥‥‥‥‥ |
|
| 端座する碁盤の横に櫻餅 ○ | 修 人 |
| 店先に知らせ文あり櫻餅 | |
| 名物の餅はあそこと桜橋 | 俊 知 |
| 墨堤の句碑をつたひて櫻餅 ○ | |
○印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。

「櫻草」第99号
2006年1・2月號
当季雑詠
| 寒椿咲いて散りけり比翼塚 ○ | 合田 俊知 |
| 狛犬の守りてゆかしき初日かな |
| 社寺めぐりめぐりめぐりて去年今年 |
| み仏の顔俯きて冬日さす |
| 雪ふるや八丁堀の水重し |
| ・・・・・・・・・ |
| 義仲寺の見えず心の時雨かな ○ |
課題句:年賀、残雪
| 年礼やエレベ-ター内華やぎぬ | 俊 知 |
| 残る雪踏みしめ児らは旅立ちぬ ○ |
| 葬列の裾を濡らすや残り雪 |
○ 印は佳句とされたもの、作品の選評があったもの等です。
村上谿聲主宰の句は巻頭句などの掲載句を除いています。
誤字、仮名遣いの誤り等がありましたらお知らせください。
△TOP
<『櫻草』掲載記事>

如雨の「啄木雑想」