このページは第10回('07/1)から第20回('08/9)までの例会記録です
谿聲主宰病臥により第19回('08/7)からは会員の互選による句会です。
このほかの例会記録
| 例会記録Ⅰ | 第 1~ 9回('05/ 7~'06/11) | 例会記録Ⅶ | 第61~69回('15/ 7~'16/11) | |
| 例会記録Ⅱ | 第10~20回('07/ 1~'08/ 9) | 例会記録Ⅷ | 第70~78回('17/ 1~'18/ 5) | |
| 例会記録Ⅲ | 第21~30回('08/11~'10/ 5) | 例会記録Ⅸ | 第79~87回('18/ 7~'19/11) | |
| 例会記録Ⅳ | 第31~40回('10/ 7~'12/ 1) | 例会記録Ⅹ | 第88~99回('20/ 1~'21/11) | |
| 例会記録Ⅴ | 第41~51回('12/ 3~'13/11) | 例会記録ⅩⅠ | 第100~111回('22/ 1~'23/11) | |
| 例会記録Ⅵ | 第52~60回('14/ 1~'15/ 5) | 例会記録ⅩⅡ | 第111~………回('24/ 1~……) |
誤字、表記違いあるいは作者名等に気づかれましたらお知らせください。
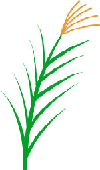
第20回句会
| <鈴木蓮囲池 選> | |
| 連山を望みて里の柿簾 ☆ | 弁慶 |
| 吊るし柿姉健在の宅配便 | 貞風 |
| 朝顔のつる軒先に迷ひけり | 仲安 |
| 秋刀魚焼く春夫の詩を口遊む | 弁慶 |
| 親潮の紺に染まりし秋刀魚かな | 游悦 |
| <高橋啓窓 選> | |
| 連山を望みて里の柿簾 ☆ | 弁慶 |
| 夜顔の大輪開き友和顔 | 隆一 |
| 新涼や御詠歌響く地蔵堂 | 三鬼堂 |
| 蜩や人の世はなど言ひさして | 如雨 |
| 朝顔市入谷は江戸の風物詩 | 蓮囲池 |
| <伊東興山 選> | |
| 母が焼く秋刀魚待つ子ら賑やかに ☆ | 啓窓 |
| 朝顔のつる軒先に迷ひけり | 仲安 |
| 渓流やヤマベ飛び跳ね秋凉し | 啓窓 |
| 天高し紺碧の空に雲一点 | 仲安 |
| 新涼や生徒の顔も大人びて | 游悦 |
| <合田三鬼堂 選> | |
| 新涼や生徒の顔も大人びて ☆ | 游悦 |
| 連山を望みて里の柿簾 | 弁慶 |
| 帰省子も去りて軒端の吊し柿 | 游悦 |
| 秋刀魚焼く潮の流れに感謝して | 隆一 |
| 親潮の紺に染まりし秋刀魚かな | 游悦 |
| <小川修人 選> | |
| 天高しはないちもんめ安芸の国 ☆ | 貞風 |
| 谷深きグランドキャニオン天高し | 游悦 |
| ともかくも国一の宮天高し | 隆一 |
| 釧路川下りしカヌー秋夕焼 | 啓窓 |
| 焼き過ぎと思うも旨き秋刀魚かな | 興山 |
| <岩渕如雨 選> | |
| 飛ばし読む推理小説涼新た ☆ | 修人 |
| 朝顔のつる軒先に迷ひけり | 仲安 |
| 吊し柿散居の村の風御堂 | 隆一 |
| 天高しはないちもんめ安芸の国 | 貞風 |
| 天高し浅間の煙棒立ちに | 蓮囲池 |
| <中野仲安 選> | |
| 連山を望みて里の柿簾 ☆ | 弁慶 |
| 新涼や御詠歌響く地蔵堂 | 三鬼堂 |
| 行きつけの店閉ぢし跡虫の声 | 如雨 |
| 天高し浅間の煙棒立ちに | 蓮囲池 |
| 新涼や生徒の顔も大人びて | 游悦 |
| <松本貞風 選> | |
| 天高く霧中に浮かぶ奇峰群 ☆ | 興山 |
| 朝顔の覆い繁りてエコ効果 | 仲安 |
| 飛ばし読む推理小説涼新た | 修人 |
| 親潮の紺に染まりし秋刀魚かな | 游悦 |
| 軒先で食欲誘ふ吊し柿 | 興山 |
| <武蔵弁慶 選> | |
| 親潮の紺に染まりし秋刀魚かな ☆ | 游悦 |
| 朝顔のつる軒先に迷ひけり | 仲安 |
| 新涼の駅に佇む古老かな | 興山 |
| 志ある句詠みたし天高し | 修人 |
| 朝顔市入谷は江戸の風物詩 | 蓮囲池 |
| <奥山游悦 選> | |
| 朝顔のわづかに揺れて雨兆す ☆ | 如雨 |
| 吊るし柿姉健在の宅配便 | 貞風 |
| 新涼や庭園灯の控へめに | 如雨 |
| 行きつけの店閉ぢし跡虫の声 | 如雨 |
| 釧路川下りしカヌー秋夕焼 | 啓窓 |
| <平山隆一 選> | |
| 秋刀魚二尾戦後は遠くなりにけり ☆ | 蓮囲池 |
| 原油高一斉休漁秋刀魚船 | 貞風 |
| 志ある句詠みたし天高し | 修人 |
| 天翔けるアポロン讃仰吊し柿 | 修人 |
| 朝一輪夕に二輪朝顔記 | 蓮囲池 |
☆ 印は特選に選ばれた作品です。
| <互選句まとめ> | |
| 4点 連山を望みて里の柿簾 ☆☆☆ | 弁慶 |
| 4点 親潮の紺に染まりし秋刀魚かな ☆ | 游悦 |
| 4点 朝顔のつる軒先に迷ひけり | 仲安 |
| 3点 新涼や生徒の顔も大人びて ☆ | 游悦 |
| 2点 天高しはないちもんめ安芸の国 ☆ | 貞風 |
| 2点 飛ばし読む推理小説涼新た ☆ | 修人 |
| 2点 吊るし柿姉健在の宅配便 | 貞風 |
| 2点 新涼や御詠歌響く地蔵堂 | 三鬼堂 |
| 2点 釧路川下りしカヌー秋夕焼 | 啓窓 |
| 2点 天高し浅間の煙棒立ちに | 蓮囲池 |
| 2点 行きつけの店閉ぢし跡虫の声 | 如雨 |
| 2点 志ある句詠みたし天高し | 修人 |
| 2点 朝顔市入谷は江戸の風物詩 | 蓮囲池 |
| 1点 母が焼く秋刀魚待つ子ら賑やかに ☆ | 啓窓 |
| 1点 天高く霧中に浮かぶ奇峰群 ☆ | 興山 |
| 1点 朝顔のわづかに揺れて雨兆す ☆ | 如雨 |
| 1点 秋刀魚二尾戦後は遠くなりにけり ☆ | 蓮囲池 |
| 他の1点句 ‥‥ 18句 | |
☆ 印は互選で特選に選ばれたものです。(☆☆、☆☆☆は多重選)
△TOP

第19回句会
<村上谿聲主宰病臥のため今回から会員互選のみの句会となりました>
| 以下、会員の互選の結果です。 選者の配列順は俳号の50音順です。 |
| <高橋啓窓 選> | |
| 雲の峰天地有情の境地たり ☆ | 弁慶 |
| 雲の峰しろつめ草の丘白く | 貞風 |
| 馬鈴薯のうす紫に道暮るる | 如雨 |
| 道の辺に仙女微笑む合歓の花 | 修人 |
| ビルの間に色街名残りの合歓の花 | 三鬼堂 |
| <小川修人 選> | |
| ビルの間に色街名残りの合歓の花 ☆ | 三鬼堂 |
| 馬鈴薯や昔の家族子沢山 | 弁慶 |
| 夏痩せの妻畑作に精を出し | 弁慶 |
| 争ひし故忘れゐて雲の峰 | 如雨 |
| 夢覚めてさよならもなし合歓の花 | 隆一 |
| <岩渕如雨 選> | |
| 打水やたちまち干され島の路 ☆ | 貞風 |
| 夏痩せの襟を正して盤に座す | 蓮囲池 |
| 打水や豆腐献上の老舗かな | 三鬼堂 |
| 声大き球児の背に雲の峰 | 修人 |
| ビルの間に色街名残りの合歓の花 | 三鬼堂 |
| <中野仲安 選> | |
| 知床や蝦夷海霧切れて勇姿みせ ☆ | 啓窓 |
| 打水の音も大地に吸はれけり | 游悦 |
| 声大き球児の背に雲の峰 | 修人 |
| 夏痩せてなほ意気盛んウォーキング | 修人 |
| 骨上げて降る坂道合歓閉じる | 蓮囲池 |
| <松本貞風 選> | |
| 声大き球児の背に雲の峰 ☆ | 修人 |
| 打水や豆腐献上の老舗かな | 三鬼堂 |
| 黒百合に託して告げる蝦夷の恋 | 啓窓 |
| 夏痩せの襟を正して盤に座す | 蓮囲池 |
| 空襲を告げしサイレン合歓の花 | 如雨 |
| <合田三鬼堂 選> | |
| 七色の飛沫従へ撒水車 ☆ | 如雨 |
| 雲の峰明日は異郷へ旅に立つ | 游悦 |
| 声大き球児の背に雲の峰 | 修人 |
| 馬鈴薯の花の果てなり地平線 | 修人 |
| 打水やたちまち干され島の路 | 貞風 |
| <武蔵弁慶 選> | |
| 馬鈴薯の花の大地ぞ北海道 ☆ | 游悦 |
| 雲の峰明日は異郷へ旅に立つ | 游悦 |
| 夏負けて華やかなりし宿の膳 | 如雨 |
| 水打てば庭の草木も家族かな | 修人 |
| 哲学堂の空を覆ひし雲の峰 | 三鬼堂 |
| <奥山游悦 選> | |
| 水打てば庭の草木も家族かな ☆ | 修人 |
| 朝露に馬鈴薯の花そぼ濡れる | 仲安 |
| 馬鈴薯のうす紫に道暮るる | 如雨 |
| 争ひし故忘れゐて雲の峰 | 如雨 |
| 夏痩せの襟を正して盤に座す | 蓮囲池 |
| <平山隆一 選> | |
| 夏痩せや座り直して句集読む ☆ | 游悦 |
| 水打てば庭の草木も家族かな | 修人 |
| 争ひし故忘れゐて雲の峰 | 如雨 |
| 知床や蝦夷海霧切れて勇姿みせ | 啓窓 |
| 骨上げて降る坂道合歓閉じる | 蓮囲池 |
| <鈴木蓮囲池 選> | |
| 馬鈴薯の花の大地ぞ北海道 ☆ | 游悦 |
| 黒百合に託して告げる蝦夷の恋 | 啓窓 |
| 馬鈴薯のうす紫に道暮るる | 如雨 |
| 打水に一時の涼抱きしめる | 仲安 |
| 馬鈴薯の花の果てなり地平線 | 修人 |
☆ 印は特選に選ばれた作品です。
| <互選句まとめ> | |
| 4点 声大き球児の背に雲の峰 ☆ | 修人 |
| 3点 ビルの間に色街名残りの合歓の花 ☆ | 三鬼堂 |
| 3点 水打てば庭の草木も家族かな ☆ | 修人 |
| 3点 馬鈴薯のうす紫に道暮るる | 如雨 |
| 3点 争ひし故忘れゐて雲の峰 | 如雨 |
| 3点 夏痩せの襟を正して盤に座す | 蓮囲池 |
| 2点 馬鈴薯の花の大地ぞ北海道 ☆☆ | 游悦 |
| 2点 打水やたちまち干され島の路 ☆ | 貞風 |
| 2点 知床や蝦夷海霧切れて勇姿みせ ☆ | 啓窓 |
| 2点 骨上げて降る坂道合歓閉じる | 蓮囲池 |
| 2点 黒百合に託して告げる蝦夷の恋 | 啓窓 |
| 2点 雲の峰明日は異郷へ旅に立つ | 游悦 |
| 2点 打水や豆腐献上の老舗かな | 三鬼堂 |
| 2点 馬鈴薯の花の果てなり地平線 | 修人 |
| 1点 雲の峰天地有情の境地たり ☆ | 弁慶 |
| 1点 七色の飛沫従へ撒水車 ☆ | 如雨 |
| 1点 夏痩せや座り直して句集読む ☆ | 游悦 |
| 他の1点句 ‥‥ 12句 | |
☆ 印は互選で特選に選ばれたものです。(☆☆、☆☆☆は多重選)
△TOP

第18回句会
| 席上講評された特選・入選句、互選句です。(ほぼ清記順) 正式には主宰作成の記録に依ります。 |
| (この会のあと間もなく主宰が病魔に襲われ、正式記録は作成されていません)。 |
| <特 選> | |
| 保津川の飛沫に遠き桐の花 ☆ | 如雨 |
| 山門に猫の寝そべる安居かな ☆☆ | 修人 |
| 花杏毀誉褒貶にかかわらず | 蓮囲池 |
| -------------------- | |
| <入 選> | |
| 日本に生れし幸せ青田かな | 游悦 |
| 定まらぬ田螺の道や風遊ぶ ☆ | 如雨 |
| 化野や緑百色石仏 | 如雨 |
| 粽解く紐の長さや古鞄 | 如雨 |
| 継之助傷つき辿る桐の里 | 弁慶 |
| 武者人形元気に育てと送りやる | 仲安 |
| 杏咲く北アルプスに千曲川 | 仲安 |
| 病の手安居の墨を磨りおろす ☆ | 蓮囲池 |
| 旅好きの女三人草団子 ☆ | 蓮囲池 |
| 君は剪る一輪挿しや桐の花 | 俊知 |
| みちのくの山澄みわたり桐の花 | 俊知 |
| 花杏今日は遠出のランニング | 貞風 |
| 菖蒲湯や子供泣く声笑う声 | 貞風 |
| 嫁に来し母は十七桐の花 ☆☆ | 貞風 |
| 縁先に心地良き風草の餅 | 修人 |
| -------------------- | |
| 春雷に蛙の合唱ふと止みぬ | 三甫 |
| 庭先の牡丹一輪朝日浴び | 啓窓 |
| 檀那寺人影見えず安居かな | 興山 |
| ---------------------------------- | |
| <互選高点句・特選句より> | |
| 3点 母逝きて明治は遠く遠蛙 ☆☆ | 蓮囲池 |
| 3点 嫁に来し母は十七桐の花 ☆☆ | 貞風 |
| 3点 山門に猫の寝そべる安居かな ☆☆ | 修人 |
| 3点 病の手安居の墨を磨りおろす ☆ | 蓮囲池 |
| 3点 旅好きの女三人草団子 ☆ | 蓮囲池 |
| 3点 無人駅遠巻きにする蛙かな ☆ | 游悦 |
| 3点 そのときが信濃への旅花杏 | 谿聲 |
| 2点 夏安居や風ひとすじに背筋立て ☆ | 隆一 |
| 2点 保津川の飛沫に遠き桐の花 ☆ | 如雨 |
| 1点 定まらぬ田螺の道や風遊ぶ ☆ | 如雨 |
(1、2点句は互選特選となったのみ載せています。) |
上段が特選、次段が佳作、下段が互選句です。
☆印は互選で特選に選ばれたものです。(☆☆は二重選)
| 主 宰 吟 村 上 谿 聲 |
| 点睛の眼が生きて鍾馗の図 |
| そのときが信濃への旅花杏 |
△TOP
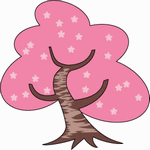
第17回句会
| 彼岸会や同胞欠けず打揃ひ | 蓮囲池 |
| <主宰評> 直系・傍系いずれにせよ尊属の供養は覚悟の上のことだが、兄弟姉妹はつらいものだ。われらが齢を重ねても「打揃ひ」というのはめでたい。 | |
| 絵踏して心閉ざせし遊女かな | 俊 知 |
| <主宰評> 神の前の平等を説いたキリストの教義は、身分制社会であった日本の最底辺の遊女に希望を与えた。しかし、「絵踏」した遊女は深く心を閉ざしたのである。原句:閉ざしし | |
| 暮れなづむ仏舎利塔や霾れり | 修 人 |
| <主宰評> 中国かインドかは知らないが、「暮れなづむ」との措辞に、「霾」の季節がぴったりと合っている。 | |
| 狐狸庵の神の沈黙絵踏かな ☆ | 如 雨 |
| <主宰評> 狐狸庵・遠藤周作の小説踏絵の苦悩を描く「沈黙」を踏まえた句。 | |
| -------------------- | |
| 黄砂舞ふ長江の空ひとつづき ☆☆☆☆ | 蓮囲池 |
| 山家集繙き偲ぶ西行忌 | 弁 慶 |
| いきなりの雪も花かと西行忌 ☆ | 如 雨 |
| もののふに花の心ぞ西行忌 ☆ | 修人 |
| 変はる町変はらぬ老舗彼岸かな | 修 人 |
| 曲水や義之が詩作の宴をはり | 弁 慶 |
| 絵踏せぬ殉教の像長崎に | 蓮囲池 |
| 春塵にマスクゴーグル怪人相 | 仲 安 |
| 霾や偏西風に乗りいにしえも | 弁 慶 |
| 傷多し思ひ出詰る古き雛 | 仲 安 |
| 旅心なほ止みがたく西行忌 | 游 悦 |
| 亡き母と夢で語らふ彼岸かな | 弁 慶 |
| -------------------- | |
| 霾らす国の横綱塩をふる | 貞 風 |
| 波入の磯穏やかに彼岸前 | 隆 一 |
| 白雪に映える紺青ニコライ堂 | 三 甫 |
| 川べりにぽつりぽつりと蕗のとう | 啓 窓 |
| ---------------------------------- | |
| <互選高点句・特選句より> | |
| 5点 黄砂舞ふ長江の空ひとつづき ☆☆☆☆ | 蓮囲池 |
| 4点 もののふに花の心ぞ西行忌 ☆ | 修 人 |
| 4点 変はる町変はらぬ老舗彼岸かな | 修 人 |
| 3点 いきなりの雪も花かと西行忌 ☆ | 如 雨 |
| 3点 暮れなづむ仏舎利塔や霾れり | 修 人 |
| 2点 狐狸庵の神父の沈黙絵踏かな ☆ | 如 雨 |
| 2点 曲水や歳時記めくり独り酒 ☆ | 修 人 |
| 1点 巡錫の秩父札所や西行忌 ☆ | 蓮囲池 |
(1,2点句は互選特選となった句のみ載せています。) |
上段が特選、次段が佳作、下段が互選句です。
☆印は互選で特選に選ばれたものです。(☆☆、☆☆☆は多重選)
| 主 宰 吟 村 上 谿 聲 |
| 容の細き眦古ひひな |
| バテレンの地の果てに遭ふ絵踏かな |
| 展覧の作家の遺書や涅槃西風 |
| 霾や唐天竺も指呼の間 |
| ベランダに紅白咲かせ花苺 |
△TOP
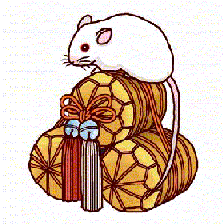
第16回句会
谿 聲 主 宰 選。 上段が特選、中段が佳作です。
| 壁の穴何れの膳か嫁が君 | 隆一 |
| <主宰評> 嫁が君という半ば空想的な季語を、壁の穴の向うに現実の舞台があるかのように提示した。 | |
| 猿曳きの人集めたり山の上 | 俊知 |
| <主宰評> 参考:猿曳きに人集ひをり山の上 ではいかが? | |
| 町駅伝年賀々々の競技場 | 貞風 |
| <主宰評> 「町駅伝」という状況設定がよい。 | |
| 飛び跳ねる孫の手を引き初詣 | 啓窓 |
| <主宰評> 神経を集中させて孫の相手をしている様子がよくわかる。爺さんは叱らないので、好かれるのだ。 | |
| 年棚の古里の神札古りにけり | 如雨 |
| <主宰評> 一句にはやや定型どおりの古さはあるが、ふるさとの思ひ出とは、まあこんなところか。 | |
| すれ違ふ破魔矢の鈴や肩ぐるま | ―〃― |
| <主宰評> カメラアングルの上手い写真家を見るようです。 | |
| 嫁が君猫人形に一目散 | 啓窓 |
| <主宰評> 猫人形を使って、落語とか漫才をやれば笑いが取れそうです | |
| 塩の道辿りし鰤の雑煮かな | 修人 |
| <主宰評> 雑煮の句であるが、ことにその具に使われている鰤が塩の道を通って運ばれて来たことに思いを致したのであろう。作者のふるさと信州が舞台の小説風俳句です。 | |
| -------------------- | |
| 香合に姿を変へて嫁が君 | 修人 |
| 往来の日向を騒ぐ初雀 | ―〃― |
| 息災の他は願はず初詣 | ―〃― |
| 人混みを怖れずに行く冬帽子 ☆ | 游悦 |
| 湯けむりの途切れし先の寒月夜 ☆ | ―〃― |
| 無為ながら至福のときぞ日向ぼこ | ―〃― |
| 抜け道の幅いつぱいに冬の月 ☆ | 貞風 |
| 滑空をして遠ざかる落葉かな | ―〃― |
| 雪虫や生まれはいずこどこへ行く | ―〃― |
| 静寂の庭にひびきし初稽古 | 仲安 |
| 獅子舞の囃を耳に昼寝かな | ―〃― |
| 帰り入る関東平野寒夕焼 | 隆一 |
| 寒紅や滑り支度の宿出口 | ―〃― |
| 配達の少年照れる御慶かな | 如雨 |
| 胡座逃る猫の欠伸や初茜 | ―〃― |
| 激動の年のシンボル嫁が君 ☆ | 弁慶 |
| -------------------- | |
| 新年に輝く富士に手を合わせ | 三甫 |
| 柚子の湯に浸りて聞きし雨の音 | 幸風 |
| 鶴見川白き息吐く散歩人 | 興山 |
| ---------------------------------- | |
| <互選高点句・特選句より> | |
| 4点 仮名のねの丸く大きく賀状来る ☆☆ | 谿聲 |
| 4点 睥睨の嘴猛々し初鴉 ☆ | ―〃― |
| 4点 激動の年のシンボル嫁が君 ☆ | 弁慶 |
| 4点 息災の他は願はず初詣 | 修人 |
| 3点 獅子舞の囃を耳に昼寝かな | 仲安 |
| 2点 初春や故郷の山凛として ☆ | ―〃― |
| 2点 抜け道の幅いつぱいに冬の月 ☆ | 貞風 |
| 2点 湯けむりの途切れし先の寒月夜 ☆ | 游悦 |
| 1点 人混みを怖れずに行く冬帽子 ☆ | ―〃― |
| 1点 温暖化蝉氷さへ今はなく ☆ | 三甫 |
| 1点 幾百の生の声聞く賀状かな ☆ | 如雨 |
(1,2点句は互選特選となったのみ載せています。) |
上段が特選、次段が佳作、下段が互選句です。
☆印は互選で特選に選ばれたものです。(☆☆、☆☆☆は多重選)
| 主 宰 吟 村 上 谿 聲 |
| 一羽翔ちいつせいに翔ち初雀 |
| 睥睨の嘴猛々し初鴉 |
| 仮名のねの丸く大きく賀状来る |
△TOP

第15回句会
谿 聲 主 宰 選。 上段が特選、中段が佳作です。
上段が特選、次段が佳作、下段が互選句です。
☆印は互選で特選に選ばれたものです。(☆☆、☆☆☆は多重選)
互選1点については特選票があった句(既掲句を除く)のみ載せています。
| 主 宰 吟 村 上 谿 聲 |
| 雄心の益荒男立てと鵙高音 |
| わが庵の神も発ちしか風騒ぐ |
| 買出しはいざ魚沼へ今年米 |
△TOP
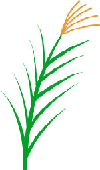
第14回句会
'07年8月5日開催の『櫻草』同人会総会で、武蔵弁慶さんが同人に推挙されました。
谿 聲 主 宰 選。 上段が特選、中段が佳作です。
| 句の一つ出来ず暮れゆく西鶴忌 | 隆一 |
| <主宰評> 井原西鶴は俳諧に浮世草子に大変名作をもってならしたものだ。それに引きかえ四苦八苦して苦吟している自分の哀れな事よという諧謔性が面白い。 | |
| 遠祖も通りし畦や曼珠沙華 ☆ | 如雨 |
| <主宰評> 「生きかはり死にかはりして打つ田かな」の鬼城句を思い出す。 | |
| 書出しの文決めかねつ秋暑し | ―〃― |
| <主宰評> 真夏の熱気も辛いが大気がゆるんでから又ぶり返す残暑は、手紙の書き出し文にも気力を振り絞らなくてはその気になれないものだ。 | |
| 稲妻におののき思ふ9・11 | 仲安 |
| <主宰評> まさに現代を注視して作句している。「9・11」 の表現により、何も言わずに多くのことを語っている。 稲妻の季語の使い方が象徴的でうまい。 | |
| 門火焚く父若きまま帰しけり | 蓮囲池 |
| 鬼芒浄瑠璃坂の死闘跡 | 俊知 |
| -------------------- | |
| 稲光夜空裂きわけいずこへか | 三甫 |
| 土濡るるほどには降らず秋の蝶 | 如雨 |
| 古座敷大の字となる残暑かな ☆☆ | 修人 |
| 外風呂に入りてひとりの残暑かな ☆ | 弁慶 |
| 稲妻に花街しばし音の絶え | 俊知 |
| 敬老といふ日の暑さ土渇く | 隆一 |
| 微風さえ捉へてみせる芒かな ☆ | 貞風 |
| 花芒夕日に礼を言ふごとく ☆ | 如雨 |
| そつと置く夜食は母のぬくもりを | 蓮囲池 |
| -------------------- | |
| 芒野に月が輝き犬走る | 啓窓 |
| ---------------------------------- | |
| <互選高点句・特選句より> | |
| 5点 古座敷大の字となる残暑かな ☆☆ | 修人 |
| 5点 門火焚く父若きまま帰しけり | 蓮囲池 |
| 3点 芒分け四界を得たり峠道 ☆ | 蓮囲池 |
| 3点 川舟や祖父の通勤花芒 | 隆一 |
| 2点 土濡るるほどには降らず秋の蝶 | 如雨 |
| 2点 夜食などなかりし頃の受験生 ☆ | 隆一 |
| 2点 書出しの文決めかねつ秋暑し | 如雨 |
| 2点 花芒夕日に礼を言ふごとく ☆ | 如雨 |
| 2点 助手席に頬火照らせて秋暑し | 谿聲 |
| 2点 そつと置く夜食は母のぬくもりを | 蓮囲池 |
| 2点 風に揺れ風のみ揺れるすすきかな | 弁慶 |
| 1点 二人旅仙石原に尾花みち ☆ | 仲安 |
| 1点 多捨多作佳き句残さん西鶴忌 ☆ | 修人 |
(1点句は互選特選となったのみ載せています。) |
|
上段が特選、次段が佳作、下段が互選句です。
☆印は互選で特選に選ばれたものです。(☆☆、☆☆☆は多重選)
| 主 宰 吟 村 上 谿 聲 |
| なほ流行る人情ものや西鶴忌 |
| 振り仰ぐ大和の空や稲光 |
△TOP

第13回句会
谿 聲 主 宰 選。 上段が特選、中段が佳作です。
| 夏座敷敷居の上に猫眠る | 如雨 |
| <主宰評> 猫や犬は、家の中の涼しい所や暖かい所を、本当によく知っている。 | |
| 半夏生竹馬の友と雑魚寝して | 弁慶 |
| 絵団扇や八尾の風を胸裡まで | 隆一 |
| 尻つぽ切り箸を逃げけり心太 | 如雨 |
| 原句‥‥尻つぽ切り箸を逃げたり心太 | |
| 結願のお礼参りや心太 | 蓮囲池 |
| -------------------- | |
| 夕立に廣重生野を思ひけり ☆ | 弁慶 |
| 鰻屋の味を引き出す團扇かな | ―〃― |
| 朝市に旬を拾ひつ半夏生 ☆ | 蓮囲池 |
| 水中り旅寝の枕離れ得ず | ―〃― |
| 団扇止め長考に入る勝負どこ ☆ | ―〃― |
| どくだみや一輪挿しの花明かり | 貞風 |
| 戦いは団扇で挑む甲子園 | ―〃― |
| 原爆忌妖しく点る骨の影 | ―〃― |
| 雲淡し羽後の車窓に合歓の花 | 如雨 |
| 坊守の茶菓のもてなし夕立晴 | 隆一 |
| 夾竹桃雲の輪郭確かなり | 如雨 |
| 夕立に軒先借りて傘借りぬ | 仲安 |
| 何事もなく暮れにけり心太 ☆ | 修人 |
| -------------------- | |
| 洗濯を干して見上ぐる夕立雲 | 興山 |
| 渓流の光に映えるヤマベかな | 啓窓 |
| 夕立に浴衣の裾をたくしあげ | 三甫 |
| ---------------------------------- | |
| <互選高点句・特選句より> | |
| 5点 戦ある世を忘れゐて合歓の花 ☆☆☆ | 谿聲 |
| 4点 退院のすぐ転た寝の半夏生 | ―〃― |
| 3点 鰻屋の味を引き出す團扇かな ☆ | 弁慶 |
| 2点 何事もなく暮れにけり心太 ☆ | 修人 |
| 2点 団扇止め長考に入る勝負どこ ☆ | 蓮囲池 |
| 2点 朝市に旬を拾ひつ半夏生 ☆ | ―〃― |
| 2点 夕立に廣重生野を思ひけり ☆ | 弁慶 |
| 2点 団扇手に踊りの輪に入るわれべたち | 仲安 |
| 2点 雨垂れのリズム早まる半夏生 | 修人 |
| 2点 坊守の茶菓のもてなし夕立晴 | 隆一 |
| 2点 心太すする口元愛らしい | 三甫 |
| 2点 夾竹桃雲の輪郭確かなり | 如雨 |
| 2点 老夫婦語らひつきて心太 | 仲安 |
| 2点 庭先は進化の途中半夏生 | 貞風 |
| 2点 戦いは団扇で挑む甲子園 | 貞風 |
| 2点 夕立に浴衣の裾をたくしあげ | 三甫 |
上段が特選、次段が佳作、下段が互選句です。
☆印は互選で特選に選ばれたものです。(☆☆、☆☆☆は多重選)
| 主 宰 吟 村 上 谿 聲 |
| 戦ある世を忘れゐて合歓の花 |
| 退院のすぐ転た寝の半夏生 |
| サングラス似合ふ町並み軽井沢 |
△TOP
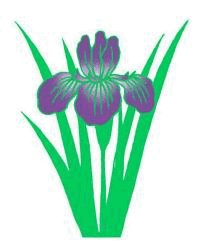
第12回句会
谿 聲 主 宰 選。 上段が特選、中段が佳作です。
| 蜃気楼カメラ居並ぶ春の海 | 貞風 |
| <主宰評> 蜃気楼を狙うカメラを通して、春の海に臨場感が溢れている。 | |
| 平穏の日々の明け暮れ立葵 | 蓮囲池 |
| <主宰評> 立葵には優雅な非日常性が隠されているようだ。 | |
| マネキンの一足先に更衣 | ―〃― |
| <主宰評> マネキンを利用するお店などでは、更衣の時期は「一足先に」なのでしょう。 | |
| 息災の日をいつくしむ新茶の香 | ―〃― |
| <主宰評> 平凡な息災の日々に、新茶を酌めば心は即ちほのぼのとなる。 | |
| 江の電の家並抜けて春の海 | 修人 |
| <主宰評> 江ノ電に沿線を行けば、期待をしている乗客には詩になる風景が現れそうです。 | |
| -------------------- | |
| 山葵田や鉄条網の守る聖地 ☆ | 青郎 |
| 青梅の三つほども落ち落着かず | 如雨 |
| 新人の声落着きぬ五月尽 | ―〃― |
| 草庵の薄暗がりや額の花 | 郁子 |
| 湧水の命を宿す山葵かな | 弁慶 |
| 松を剪る音と新茶を楽しめり | 隆一 |
| 水音を辿り来れば山葵生ふ ☆ | 郁子 |
| 更衣天の香具山思ひけり | 弁慶 |
| 生業のほろ苦きこと新茶噛む ☆ | 貞風 |
| 春の日や子の靴音に覚えあり ☆ | ―〃― |
| 風孕む九条守れ鯉幟 | 修人 |
| 病癒えふるさと旅す花山葵 ☆☆ | ―〃― |
| -------------------- | |
| 更衣今は不要の自由人 | 竹風 |
| 釣り糸にひたすら見入る春の海 | 興山 |
| ---------------------------------- | |
| <互選高点句・特選句より> | |
| 3点 山葵田や鉄条網の守る聖地 ☆ | 青郎 |
| 3点 平穏の日々の明け暮れ立葵 | 蓮囲池 |
| 3点 息災の日をいつくしむ新茶の香 | ―〃― |
| 3点 巡礼の憩う瀬戸内春の海 | 俊知 |
| 2点 夕餉には摘み来し三ツ葉ひとり酒 ☆ | 青郎 |
| 2点 春の池水輪とろりと拡がりぬ ☆ | 隆一 |
| 1点 愛蔵の竣介絵売り新茶飲む ☆ | 弁慶 |
| 1点 大輪の芍薬咲きぬ更衣 ☆ | 幸風 |
(1,2点句は互選特選となったのみ載せています。) |
|
上段が特選、次段が佳作、下段が互選句です。
☆印は互選で特選に選ばれたものです。
(☆☆、☆☆☆は多重選)
| 主 宰 吟 村 上 谿 聲 | |
| 島蔭に落暉消えゆく春の海 | |
| 梅雨近しやらねばならぬこと数多 | |
△TOP
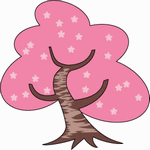
第11回句会
谿 聲 主 宰 選。 上段が特選、中段が佳作です。
席上主宰の講評があった句です(ほぼ清記順)。
仮作成の記録には主宰特選評の記載は未済です(結局作成されませんでした)。
| 浜離宮梅に誘われ都鳥 | 俊知 |
| 春宵や清水焼の猪口に酌む | 如雨 |
| 雪解の水のささやくひとりごと | 弁慶 |
| 花三分尊徳ひとり薪負う | 貞風 |
| つちふるや五重塔の黄昏るる | 修人 |
| -------------------- | |
| 友が逝き春一番が荒れ狂う | 三甫 |
| 石楠花の紅解けゆく旅の宿 ☆ | 遥女 |
| 歳時記をポトリ落せり目借時 | ―〃― |
| 豪商の白壁朽ちて春の雨 ☆ | 弁慶 |
| 磐梯の真白き峰や春の風 | ―〃― |
| しばらくは心静かに花李 | 修人 |
| 風通る山門脇に桜草 | ―〃― |
| 春爛漫ふと思い出す父の笑み | 幸風 |
| 春風に小蜘蛛が飛んで銀の糸 ☆ | ―〃― |
| 春の陽や何事もなし子規の墓 | 俊知 |
| 朝寝していまだ覚めざる猫と居る | 如雨 |
| 人形の髪漆黒に桃の冷え | ―〃― |
| ---------------------------------- | |
| <互選高点句・特選句より> | |
| 5点 春めくや斑にゆるむ浅間山 ☆☆☆ | 谿聲 |
| 4点 豪商の白壁朽ちて春の雨 ☆ | 弁慶 |
| 4点 彩雲の西へ隊列鳥帰る ☆ | 修人 |
| 4点 人形の髪漆黒に桃の冷え | 如雨 |
| 3点 残り鴨汝には汝の道あらん ☆☆☆ | 谿聲 |
| 3点 取り出すは去年の埃りの種袋 | ―〃― |
| 3点 野萱草土手に芽吹きて勢揃ひ | ―〃― |
| 3点 雪解の水のささやくひとりごと | 弁慶 |
| 3点 白薔薇の十四五本へひとり言 | 遥女 |
| 2点 江戸前の凪海苔舟の日和あり ☆ | 蓮囲池 |
| 1点 白梅下特年兵の殉国碑 ☆ | 俊知 |
(1,2点句は互選特選となったのみ載せています。) |
上段が特選、次段が佳作、下段が互選句です。
☆印は互選で特選に選ばれたものです。(☆☆、☆☆☆は多重選)
| 主 宰 吟 村 上 谿 聲 |
| 春めくや斑にゆるむ浅間山 |
| 残り鴨汝には汝の道あらん |
△TOP

第10回句会
谿 聲 主 宰 選。 上段が特選、中段が佳作です。
| 列車待つ不動の駅員息白し | 俊知 |
| <主宰評> ローカル線の通過駅などで、ただ見送るだけの職務で直立している駅員など、ポッポ屋を連想する。 | |
| 百歳を重ねし母と大晦日 | 幸風 |
| <主宰評> 一寸やそっとのことでは体験できない大晦日の幸せな家族の情景です。 | |
| 漱石忌素知らぬ顔の猫過ぎる | 如雨 |
| <主宰評> 漱石といえば名前のない猫がシンボル。この猫は知らないだろうが、今日は漱石の忌日なのだよ。 | |
| 愚管抄先まだ厚し寒日和 | 隆一 |
| <主宰評> 勉強家の隆一氏をもってしても、名だたる愚管抄を読み込むのは溜息が漏れそうな宿題のようです。 | |
| 蝋梅や神戸の悪夢醒めやらず | 仲安 |
| <主宰評> 当事者にはテレビなどで見る追悼記事の何百倍の恐ろしさ、無念さが残ることでしょう。蝋梅が妙。 | |
| -------------------- | |
| 知らせ受け急く足重く息白し | 仲安 |
| 賀状来ぬ友の安否を気遣いし | -〃- |
| 灯の下を息白き人歩の合ひて | 如雨 |
| 顧みず繰りごと言はず大晦日 | -〃- |
| 初詣天狗うちはと下山かな | 修人 |
| 浩然の気保ちゆかん漱石忌 ☆ | -〃- |
| 鵠三羽見詰る我も息白し☆☆ | 隆一 |
| 谷中路を草臥れたれど七福神 | -〃- |
| 文明の危うさ想う漱石忌 | -〃- |
| 息白し殺気立つ輪にせりの声 ☆☆ | 蓮囲池 |
| 遠耳の母も輪に居る大晦日 ☆ | -〃- |
| 小人の見上げる巨石漱石忌 ☆ | 俊知 |
| 初不動比翼が塚へ涙雨 | -〃- |
| 初えんまヤットコ隅へ閻魔堂 | -〃- |
| 鳥待ちて蕾ふくらむ庭の梅 | 興山 |
| 気がつけば老老介護の七日粥 | 幸風 |
| 大晦日大地に染みる時の音 | 貞風 |
| オホーツク羽ばたき降りて息白し ☆ | 武司 |
| ------------ | |
| こがらしや又も友逝くさびしさよ | 竹風 |
| -------------------- | |
| <互選高点句・特選句よ り> | |
| 5点 息白し殺気立つ輪にせりの声 | 蓮囲池 |
| 4点 顧みず繰りごと言はず大晦日 | 如雨 |
| 4点 初詣天狗うちはと下山かな | 修人 |
| 3点 愚管抄先まだ厚し寒日和 | 隆一 |
| 3点 豁然と富士現はるる息白し ☆ | 修人 |
| 3点 灯の下を息白き人歩の合ひて | 如雨 |
| 3点 百歳を重ねし母と大晦日 | 幸風 |
| 3点 病身の妻と鐘聞く大晦日 ☆ | 仲安 |
| 2点 隠居老思いは無色屠蘇旨し ☆ | 幸風 |
| 1点 松代は中将の墓冠雪 ☆ | 隆一 |
(1,2点句は互選特選となったのみ載せています。) |
上段が特選、次段が佳作、下段が互選句です。
☆印は互選で特選に選ばれたものです。(☆☆、☆☆☆は多重選)
| 主 宰 吟 村 上 谿 聲 |
| こはごはと安否問ひけり初電話 |
| 犬好きは犬のこと書く漱石忌 |
△TOP
| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| < 会 員 > | |||||
| | |||||
| 谿 聲 : | 村上 幹也 (主宰) |
蓮囲池 : | 鈴木 錬一 | ||
| 幸 風 : | 小林 幸司 | 隆 一 : | 平山 隆一 | ||
| 三鬼堂: (俊知改メ) | 合田 俊知 (「櫻草」同人) | 貞 風 : | 松本 貞 | ||
| 仲 安 : | 中野 安弘 | 弁 慶 : | 武蔵 好彦 | ||
| 如 雨 : | 岩渕 上 | 武 司 : | 内山 武司 | ||
| 修 人 : | 小川 修 | 竹 風 : | 加賀美 一 | ||
| 興 山 : | 伊東 興三 | 青 郎 : | 坂口 二郎 (客人)(「櫻草」同人) | ||
| 遥 女 : | 小松 洋子 (客人) |
三 甫 : | 三浦 器允 | ||
| 郁 子 : | 村上 郁子 (客人)(「櫻草」同人) |
啓 窓 : | 高橋 啓悟 | ||
| 游 悦 : | 奥山 興悦 | ・・ | :・・ | ||
| (掲 出 順) | |||||
△TOP
240206、例会記録ⅩⅡのLink追加。
